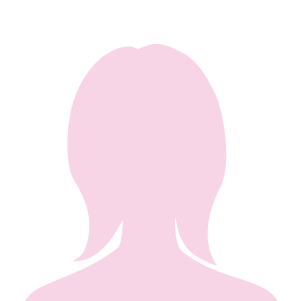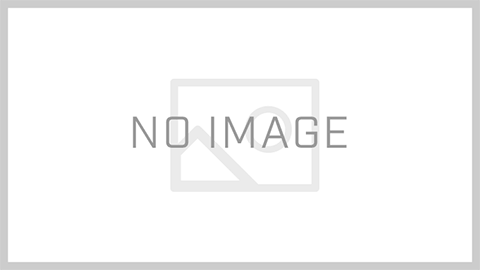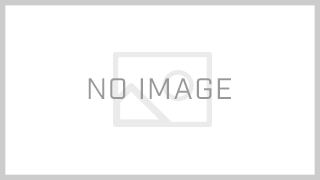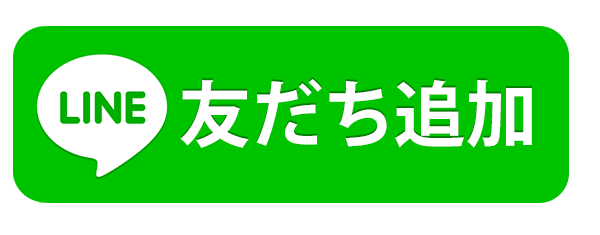こんにちは。えとかしです。
共働き家庭の最大の壁と言ってもいい長期休暇。
特に「小学生の夏休み」を共働き家庭がどう過ごすか、
悩んでいるご家庭も多いのではないでしょうか?
実は、それが小学校低学年で一番多い選択肢です!
でも、ふとSNSをみると
小学生のいる共働きの家庭でも
「夏休みは子ども達だけ実家へ…」
「家族旅行✈」
の文字に、なんだか心がモヤモヤ…
「うちはこのままで、本当にいいのかな?」と心が揺れることもありますよね。
実家が近くに無い、近くにあっても頼れない。
学童を使いたくても、定員オーバーで入れなかった…そんな話もよく聞きます。
そんな小学生の夏休みを、他の共働き家庭はどうしているのか?をまとめてみました。
共働き=学童 ではなく
学童以外にも、色々な選択肢を知ってるだけで、
もし子どもが「学童行きたくない!」となっても安心できますよね。
特に共働きの小学生の夏休みは、学年が上がるにつれて、過ごし方も変わってくるので、
そうした学年別での過ごし方もまとめています。
それではどうぞ!
小学生の夏休みは共働き最大の壁 学年ごとの過ごし方を紹介
共働き家庭で、保育園に通わせていた家庭にとって
夏休みはせいぜいお盆の1週間程度。
そんな家庭も多いのではないでしょうか。
でも小学生になると1か月以上にわたる夏休みが始まります。
加えて、春休みと冬休みもそれぞれ2週間程度。
保育園時代には無かった長期休暇が一気に増えることに
ドキドキしていませんか?
具体的には、
日中、子どもを預ける先確保
宿題や生活リズムの管理
毎日の昼食の準備
この記事では、そんな共働き家庭のために、
-
小学生の夏休みによくある悩み
-
子どもの預け先の選択肢一覧
-
学年ごとに異なる夏休みの過ごし方のリアル
について、体験談も交えながらわかりやすくご紹介します。
共働き家庭小学生の夏休みの困りごと
本当に至れり尽くせりだったんだな…
こんな愚痴がこぼれるくらい、
小学校と保育園・幼稚園のギャップは大きいです。
そんな中迎える小学生の夏休み。
具体的に3つの悩みが発生します。
【悩み①】子どもだけで留守番できるのか問題
まず1つ目の大きな悩みが、
「子どもを家でひとりにして大丈夫なのか?」という問題です。
多くの共働き家庭が「学童保育」を利用していますが、
地域によっては、希望する家庭全てが学童保育を利用できるわけではありませんよね。
その結果、
-
学童に入れなかった
-
学童が就業時間より早く終わってしまう
-
一部の時間帯だけ、子どもがひとりになる
という状況に置かれる家庭も少なくありません。
【親の心配】「もしもの時に、どうやって連絡を取るの?」
「大人がいない間に事故やトラブルがあったらどうしよう…」
これは、私たち親にとって最も大きな不安のひとつですよね。
そのため、連絡手段の確保は必須です。
【解決策】まだスマホは早い…そんなご家庭におすすめの“見守りデバイス
でも、
-
まだスマホは早いかな…
-
キッズケータイを持たせるのは少し不安…
そんな方におすすめなのが、
GPS機能付きの“見守りデバイス”です。
特徴:
-
事前に登録した保護者アプリに通知が届く
-
通話機能がないため、ネットトラブルの心配も少ない
-
ボタン一つで現在地通知、SOS発信などが可能
「スマホやケータイはまだ早い…」と感じるご家庭は、
まずこうした連絡ボタン付きGPSを取り入れてみるのも
安心への第一歩です!
【悩み②】子どもの昼食の準備問題
学童に預ける場合はお弁当が一般的ですよね。
最近では、昼食を提供する学童も増えているようです。
例えば、茨城県境町では2021年から学校給食センターの給食が学童でも提供されていたり、
東京都港区では、2023年からお弁当配送業者を導入。自治体が配送料を負担してくれるなど、
「長期休暇中の学童お弁当問題」は、改革が進んできています。
お住まいの地域でも、独自の取り組みが進んでいるかもしれません。
市区町村の公式サイトや学校配布の資料を確認するのがおすすめです。
とはいえ…「自宅で留守番」の場合は?
学童ではなく、子どもが家で過ごす場合
栄養バランスを考えた昼食を、忙しい朝に毎回用意するのはとても大変ですよね…
そこでおススメなのは、
冷凍のお惣菜ストックです!
定期宅配にしていると、
といった、直前の融通がきかない…なんてことが起きてしまいます。
急なお休みも“おまもり冷凍”が安心
また、急な体調不良で学童を休み、
回復した後は、子どもだけで1日念のため様子をみる。
そんな日も発生するかもしれません。
そこで
こうした冷凍のお惣菜を準備しておけば
好きなおかずを温めるだけで済むので、
小学1年生でも1人で作ることができるんです✨
日ごろ手作り派のあなたでも、こうした「おまもり」があると、
「なんとかなる」安心感が生まれますよね。
忙しい共働き家庭にとって、
「昼ごはんの心配がひとつ減る」だけでも、
夏休みのストレスはぐっと減らせますよ。
【悩み③】夏休みの宿題をこどもだけで任せて良いか問題
夏休みといえば、
毎年立ちはだかるのが…そう、宿題の壁。
どの時代の子どもでも、
「たくさんある宿題を期日内に終わらせられるのか…?!」
という大きな壁が…(笑)
毎日の宿題と違って、夏休みの宿題はとても量が多いです。
なので、
たくさんの宿題を一度に渡されて、フリーズしてしまう
量に圧倒されてしまうんです。
もちろん学童でも、「みんなで勉強する時間」を設けているのですが
基本は自習。
学習指導は、基本的に行われていません。
つまり、
と思っていると、
気づいたら“真っ白なワーク”が最終週に残っていた…なんてことも…(ホラー話)
そうした時におすすめなのは、
夏休みカレンダーを作成する事です。
我が家も毎回自作しているのですが、
夏休みの宿題が発表される1学期の保護者会から夏休みが始まる前に決めていきます。
決める順番は以下の6ステップです。
① 子どもが「夏休みにやりたいこと」をすべて書き出す
② 現実的にできそうなことを、家族会議でピックアップ
③ カレンダーに家族の休日・イベント予定を書き込む
④ やりたいことを“日”に振り分けていく
⑤ 残りの空き日に、宿題を振り分ける
⑥ 完成!
カレンダーは“守る”より“ズレても戻せる”が大事
もちろん計画通りに進まない日もあります。
でも、2〜3日ごとに進み具合を親子で確認するだけでも、
最終週に焦らずに済む仕組みができます。
詳しいカレンダーの作り方は、別記事でご紹介。
カレンダーの作成テンプレートや、実際の書き方などは、
こちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
共働き家庭小学生の預け先 学童や祖父母の家、サマーキャンプ
学童保育
日ごろ通っている学童に、
引き続き通うのが一番初めに考えられる方法ですよね。
お住まいの市区町村ごとに異なりますが、
公立の学童保育の利用時間は朝8時~夕方6時まで。
午前中は勉強する時間があったり、
おやつの時間や同年代の友人もいて涼しい部屋で体を動かせる場所がある。
一人っ子家庭も多いので、こうした子どもの居場所は大変助かりますよね。
お弁当が必須だったり、夕方にはしまってしまうといった問題はありますが、
子どもを見てくれる専任の職員がいること。
子どもが過ごしやすい環境が整っていること
これらは、親にとって一番安心できる場所かもしれません。
夏休みのみ、民間の学童に通うというケースも考えられます。
民間の学童は、先に紹介した昼食サービスを提供している場合も多く
日中の遊びの提供だけではなく、「習い事」や「理科実験教室」など
子どもの夏休みを「ワクワクしたものに」
そうしたサービスが充実しています。
日ごろ、学童を利用していない家庭も、イベントのある曜日だけ民間の学童を利用するケースも。
なので、お子さんと相談しながら、
楽しそうなイベントがやっている日は民間学童を利用してみるなど
「使い分け」も検討してみてくださいね
祖父母や親族の家
遠方の祖父母の家や親せき家へ1週間や2週間預かってもらう。
そうしたご家庭もありますよね。
家族と離れて過ごす体験も夏休みの醍醐味かもしれません。
この方法で気をつけなければいけないのは、
相手の気持ちをきちんと聞くことです。
仲の良い親族でも、
長期間子どもを預かるのはやはり色々と心配するものです。
期間やその間に発生する食事代など、
お金に関する事はとくにこちらから聞くのが大切です。
断られた場合は、事前に相手が喜びそうなものを送るなど事前に対応しておくと相手も気持ちよく迎えてくれるでしょう。
サマーキャンプ
習い事や、近くにある教会やお寺など、
サマーキャンプを開催している団体は多いです。
1泊から1週間など様々な日程がありますが、
低学年で初めての宿泊行事などは、1泊からがおすすめです。
普段体験出来ない様な大自然の中、親元を離れて過ごす体験は、
1泊でも、とても貴重な経験です。
我が家の子ども達は毎回サマーキャンプに参加していて、
川遊びが大好きになりました。
また、親元から離れて過ごす事にもすっかり慣れて
スキー合宿にも「自分から挑戦する」と、無事に滑れるように!
こうした子どもの経験の幅が広がる体験は、長期休暇中にぜひさせてあげたいですね。
ファミリーサポートとシッター
多くの行政機関で行われている「ファミリーサポート」
こちらは、子どもが未就学児のころに利用していた方も多いのではないでしょうか。
帰宅時間がどうしても遅くなる。
そんな曜日もあったり、
平日は毎日夜8時にしか自宅に帰れない。
そんな方は夕方6時に学童が終わって約2時間の留守番に
内心ヒヤヒヤすることもあるでしょう。
正直、そうした「不安」が心の中にあると、仕事に集中できないこともあると思います。
そんな時に、家の近くの「ファミリーサポート」のご家庭に預かってもらえると助かりますよね。
また、そうした地域の交流があると、
災害などが起きた緊急時にも助け合えることも考えられます。
もし、子どもが自宅でゆっくりしたいと言った場合は
民間の「シッター」を利用するのもおすすめです。
そう驚く方もいますよね。
シッターサービスを行っている会社の多くは、小学生まで扱っているところが多いです。
学童のお迎えと、夕飯の準備をお願いする。そんな使い方もできたらうれしいですよね。
共働き家庭小学生 学年別の過ごし方
これまで紹介したのは、初めて小学校の夏休みを過ごす方に向けた紹介をしていきました。
そうした方で、気になるのはこの先もこうした過ごし方になるのか?ということです。
6年間ずっと同じ夏休みの過ごし方をしてきた。
と言うお子さんは少ないのではないでしょうか。
それぞれのご家庭の事情もありますが、子どもが大きくなるにつれて、
事情も変わっていくでしょうし、「休みはこうしたいんだ!」という想いがでてくることもあるでしょう。
そうした「心」の成長を感じる、学年別のよくある夏休みの過ごし方をご紹介します。
小1~小2 学童保育ですごす割合が高め
先ほどから紹介している通り、
低学年の間は、学童に通っている家庭が多いため
夏休みも、学童を利用するお子さんが多いです。
他にも、親族に預かってもらったり、サマーキャンプに挑戦することも。
小3~小4 家で留守番、児童館で友達と遊ぶ
9歳~10歳ごろになると、
「周りと自分を比べる」ことが増えていきます。
これまで、学童に通うことに何も言わなかった子どもでも
「〇〇ちゃんは夏休み家で過ごすんだって。どうして私は学童に行かなきゃいけないの?」
と、少し困った質問が出てくる時期です。
好きな習い事も始めて、その練習もあると
自然と学童から離れていくケースもよく聞きます。
そうした変化が一番起こりやすいのがこの小学3年生~小学4年生です。
一人でお留守番する事が増えたり、
友だちと約束をして遊ぶなど、これまでにない過ごし方に子どもは「ワクワク」します。
一方で、大人のいない家に子どもだけで集まってトラブルも発生する時期なので、
一人で留守番することになったら、ぜひ家族内でのルールを作る事をおすすめします。
我が家のルールはこちら
家に居ても戸締りをする
インターフォンが鳴っても、対応しない
地震や家事など災害時の対応を決めておく
火や刃物を使わない
子ども同士で約束をして、遊ぶことも増えていきますが
一番苦労するのは約束です。
今は固定電話もない家庭も多く、連絡網などもありません。
そこで、子ども同士の連絡先交換をするかどうか判断する時期でもあります。
ぜひ、家族内でもお互いが納得するルールを作っていきましょう。
小5~小6 夏季講習に通う割合が増える 習い事が本格化
小学校高学年になると、勉強についていけない科目も増えていきます。
そうした苦手を補うために、夏季講習から塾デビューする家庭も多いです。
それ以外にも、「中学受験」の塾が本格的に始動するので
これまで一緒に遊んでいたメンバーと遊べない。
そんなことも。
「いつも遊んでいるメンバーと一緒の塾に行きたい」と言うようになったパターンも聞きます。
もしくは、習い事が本格化していって週に2日~3日練習がある。
そんな日常になり、毎日の預け先に困る日常から
スケジュール管理が必須な毎日に。
身体も大きく、口も達者になるので勘違いしてしまいますが(笑)
まだまだ子どもなので、あまり大きな負担をかけない過ごし方を見守りながら提案していきたいですね。
共働き家庭小学生夏休みを楽しむには
共働き家庭が夏休みを思いっきり楽しむには、
事前の準備が8割、残りの2割は体調管理だと思います。
事前に分かる壁の対応をしっかり調べて準備しておくこと。
そして、緊急事態になった時の為の対応も決めておけば
約40日間の夏休みも無事に過ごしていけるでしょう。
色んなことに挑戦できるようになる小学生なので、
すこし背伸びをしつつ、しっかり親のサポートをして楽しい夏休みにしたいですね。
次は、先ほども少し触れた夏休みのスケジュール管理についてです!